トランプ関税
トランプ第2期政権が発足して100日、振り返ってみると矢継ぎ早の政策発表でほぼ日替わりで情勢が変化、市場参加者もこれに振り回される日々だった。マーケットに及ぼした不確実性という意味では、やはり4月初に発表された相互関税の影響が群を抜く。ほぼ全ての貿易相手国を対象に基本税率10%を設定した上で、対象国の対米貿易収支や非関税障壁などを基に上乗せ税率を加算する方式だが、税率根拠の不透明さはもとより、中国、メキシコ、カナダといった従来のターゲット国を超えての一方的な措置は大きなサプライズとなった。大幅な株安を伴うリスク回避トレンドが加速、直後に設定された90日間の猶予期間により多少の戻しはあったが、依然として不確実性が極めて高い状況に変わりはない。
今回インドネシアに課された関税率32%は、アセアンの他国、ベトナムの46%、タイの36%に比べると低いが、それでも50%〜11%に分散する全対象国の中では高い部類に入る。インドネシア政府の交渉団は4月中旬に米国入りして初回の交渉を終えたが、ベトナムやインドらと共に、先行して交渉開始したグループに入っており、また早くから米国からの液化石油ガスの輸入増加、国内非関税障壁の引き下げ意向を表明するなど、かなり前向きな交渉姿勢がうかがわれる。
初回交渉の後、関税交渉団に加わった方に話を聞く機会があったが、今回の関税交渉を梃子に、国内の改革、つまり輸入許可運用や国産化比率の見直しを含めた投資環境改善につなげていきたいとの強い意欲が感じられた。一方、インドネシアにとって最大の貿易相手国である中国との関係についてはほとんど触れようとしなかったことも印象に残った。
中国はインドネシアの輸出先の24%を占めるが、米国向けは10%に過ぎない(2024年実績)。他のASEAN各国もベトナムなど一部を除くと貿易における対中依存度が対米依存度を上回っているが、今のところトランプ関税に対しては米国側の意向を一定程度受け入れようとする交渉スタンスが目立つ。
いま足下で起こっていることを少し長期的な視点で見ようとするならば、これまで経済的な関係のみで判断できたことがそうはいかなくなってきた、ということになるかもしれない。ASEAN各国は長らく続いた自由貿易体制の下で、経済的には概ね中国(特に需要家および投資家としての中国)に依存する一方、安全保障については米国のプレゼンスに期待するという側面が強かった。米中対立が経済から安全保障まで広範かつ急速に深まる中で、おのずと前提は変わってくる。この流れは米国でトランプ以外の誰かが大統領になったとしても当面変わらないであろう。
インドネシアにとってもこの潮流がさまざまな分野で変化のカタリストになるかもしれない。例えば産業政策においては、ジョコウィ政権下で進んだナショナリスティックな政策(厳格な輸入許可と国産化比率規制、中国資本に依存した資源下流化など)から、OECD加盟も梃子にした投資環境重視の政策へのシフトが起こるかもしれない。もちろん、逆のシナリオも考えられよう。インドネシアの産業にとって中国は需要家としての役割から価格破壊をもたらす競争相手の側面が強まってきているが、中国側がこれをうまく調整して何らかの便益(迂回輸出拠点としての地位など)をもたらすことができれば、別方向への政策シフトもあり得る。今の関税交渉の行方はこのような長期シナリオの分岐点としても捉えられるかもしれないと感じている。(三菱UFJ銀行ジャカルタ支店長 中島和重)
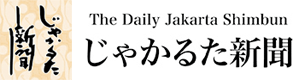




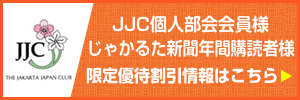


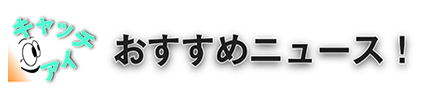












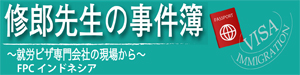





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について