ソブリン格付け
2月はインドネシア株がかなり売られた月となった。上場銘柄の加重平均で構成されるジャカルタ総合指数は、2月単月で12%下落。東南アジア他国の株式市場もトランプ関税の影響などもあって軟調に推移したが、インドネシア株は中でも最も大きい下落幅となった。
同じように債券市場でも外国人投資家によるインドネシア国債の売りが目立った。特にダナンタラの発足や財政運営への懸念が高まった2月最終週は、株・債券市場から約9億ドルの資金が国外に引き上げられ、これがルピア安を推し進めた。単一週の金融市場の資金流出としては過去1年半ぶりの規模だ。3月に入って米系金融機関によるインドネシア国債および株式に対する投資推奨の下方見直しのニュースもあり、ややこのところのマーケットにおけるネガティブな動きに懸念を持つ向きも増えてきている。
一方で、先週は大手格付機関フィッチより、インドネシアのソブリン格付けを現状の「BBB」、見通しも「安定的」で据え置くとの発表もあった。ソブリン格付けは、国債の発行元である国の信用力を格付けしたもので、マクロ経済全体や財政の状況といったファンダメンタルズを中心に評価するので、狭義のカントリーリスクといった捉え方もできよう。
インドネシアの現状のBBBは投資適格に属し、投資不適格とされるBB+以下よりも2段階上なので、仮に状況が悪化したとしてもまだある程度の安心感はある。アジアではフィリピンと同水準、タイとマレーシアは1段階上のBBB+だ(フィッチ以外の2社の大手格付機関S&P、ムーディーズも同様の評価)。
今回のフィッチのレポートを見ると、インドネシアの今の格付けは大きく2つの要因に依拠していることが読み取れる。一つめは中期的な時間軸で見た成長力の高さ。フィッチによる同じBBB国のGDP成長率予想は中央値で3・3%、インドネシアの5%は多少落ち込んだとしてもまだ高成長の部類に入る。2つめは相対的に低い政府債務。GDP対比の政府債務は40%程度と、同じくBBB国の中央値58%を大きく下回る(ただインドネシアは一方で低い税収や資源依存などによる歳入ベースの弱さも指摘されており、その分政府債務も低く抑えておく必要がある)。いずれにせよ全体としてはBBB国の中でも悪くない位置につけていると言うことができよう。
同レポートは、今後格付けの上げ下げに影響を与える可能性のあるポイントにも言及している。当然、上記の2つの要因とも一部関連するが、政府歳入がどれだけ強化・安定化されるか、外貨準備の水準が維持されるかどうか、司法の透明性や汚職への対応といったガバナンスの動向、といったようなポイントが挙げられる。
整理すると、今のインドネシアは、現実的なリスクとして格下げを心配するほどの状況には至っていないということになろう。ただ、財政のバランスシート(負債や外貨準備)は良好である一方、収益力(歳入)は相対的に弱めという特徴があることには留意が必要だ。もし仮に、今後数年で経済成長が鈍化してくる、資源価格も低調、といったような展開になってくると状況は一変するかもしれない。政府としては、成長力が持続するうちに、歳入源やガバナンスの強化など打つべき手を打っておくことが大事なのは言うまでもないだろう。(三菱UFJ銀行ジャカルタ支店長 中島和重)
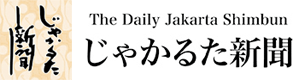




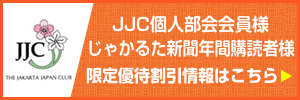


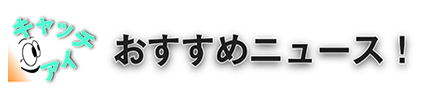












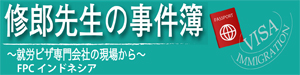





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について