【事例で学ぶ 経営の危機管理 第三回】 ストライキ編 年次昇給を発火点に労組が警告書
架空の企業を取り巻く状況を通じて、危機管理コンサルタントの後藤輝久氏からインドネシアでの経営のポイントを学ぶ本連載。今回はインドネシアの製造子会社「ABC精機」が舞台だ。同社では5月に突如として労働争議が表面化した。発端は年次昇給で、現地従業員組合は「約束より1割も少ない」と主張し、会社側に改善を迫った。組合代表は工場門前でビラを配布し、正式な回答が得られなければ6月1日から全面ストライキに突入すると宣言。門外の街頭でも支持を募る動きが活発化し、現地メディアが報じ始めると一気に注目度が高まった。
■日本側で緊急BCP―製造代替ラインを確保
静岡県にある親会社の本社は危機感を強め、極秘裏に緊急BCP(事業継続計画)の策定に着手した。具体的には、一部製品の生産を日本国内にある静岡工場へ振り替え、同時に在庫の積み増しに動いた。また、労組の動きに関わらず事業が止まらぬよう、仮事務所や輸送ルートの確保など、水面下で「最悪の事態」への備えを固めた。こうした情報は現地子会社には限定共有としつつ、現地子会社社長は「ストが行われても会社はつぶれない。スト実施になれば会社は毅然として対応する」と現地ローカル経営陣に説明して動揺を抑えた。
この情報は組合員にも漏れ、このままでは解雇されると組合員にも動揺が走ったが、組合執行部は上部団体と協議を続けつつ強硬路線を維持した。
■デッドロック回避―議事録に“協議継続”明記
一方、現地経営陣と組合の二者協議は平行線をたどった。会社側は業績不振を理由に「昇給額を約束したことはないし、法令違反はなくこれ以上の昇給は無理」「ストをしたら違法ストになるし無給、懲戒処分や解雇辞さず」との立場を譲らず、組合は「昇給に関する労使合意に違反しており違法」「労使合意違反なので有給の合法スト」と強硬に反発した。
らちが明かないため、県労働局の斡旋員を加えた三者協議に移行する運びとなった。ここでも会社側は協議を誠実に続けつつ、譲歩を小出しに留める。そして協議の議事録には「争点については継続協議中」との一文を確保し、「デッドロック」や「協議失敗」などの文言による合法ストの要件を満たしたと言われないよう慎重に言質をコントロールした。
■社内監査で労働法令違反をゼロに
並行して親会社は社内監査チームを現地に派遣し、就業規則や残業手当の計算など、労務関連の違反リスクを徹底的に洗い出した。万が一の法令違反が見つかれば即座に是正。労働問題における「会社の弱み」を事前に摘むことで、反撃材料を相手に与えない狙いがあった。労務関連だけでなく、環境(産業廃棄物)、税関、税務などについても法令違反がないことを確認した。
■スト実施に向けた準備
会社に忠実な従業員で極秘チームを作り、組合員200人に何度も通知等を迅速に郵送できるように準備を行った。メガホン、録画機材、CCTV等の整備、製造機械等の重要資産保全、配電・給水コントロール、外塀の修繕、飲料水や医薬品等備蓄の整備など多くの作業を短期間に遂行した。
一部会社寄りの従業員宅に組合員が押しかけてきたため、その従業員と家族をホテルに退避させるなどの措置もとった。
■門前バリケードとSNS炎上
会社側からの「ストライキの実施は違法であり懲戒処分の対象となる」の事前警告にもかかわらず、6月1日早朝、組合は予告通りストライキに突入。女性組合員を前列に据え周辺工場からの応援も得た抗議デモが工場門前を封鎖し、物流車両の出入りを止めた。またSNS上では「日本企業による不当搾取」のハッシュタグが拡散し、地元県議やNGOの現場視察が行われるなど、社会的非難が一気に高まった。会社前の道路も封鎖され、周辺工場の通行にも障害が発生した。さらに一部が在インドネシア日本大使館前で抗議活動を試みた。
■乱戦のなか違法スト参加者の解雇
会社側は速やかにスト参加組合員への呼出状を送付。会社の説得で最終的に200人のうち70人が自主的に職場復帰し、残る130人については懲戒解雇の措置を取った。この時期に労働局と環境当局による立ち入り監査もなされたが、事前に「弱み」を摘んでおいたので無事切り抜けた。また、緊急BCPと日本での代替生産により、顧客への製品供給は滞らずに済んだ。
■操業再開まで6週間
最終的に裁判所で会社側の主張が認められ、違法ストを続けた組合員は全員懲戒解雇が確定した。彼らは懲戒解雇通知後も工場封鎖を続けたが、会社の緻密な対策で、職場復帰者を中心にスト開始後6週間後にようやく操業再開となった。事前に蓄えた在庫と外部協力企業の活用により、納期遅れなどの重大被害は回避できた。
今回の経験を踏まえて従業員の権利に関する諸規定を再度明確化し、地域CSR活動を拡充、従業員との信頼回復を図っている。危機を乗り越えた末に得られた教訓は、労使関係の綿密な管理とBCPを含む総合的な対策の重要性であった。
◆助言 ストライキに対応するには
①危機管理の鉄則:大きく構えて小さくまとめる
この鉄則をスト対応に活用し、兆候段階で迅速に立ち上がり、各種対策を分厚く実施するべし。
②BCPは〝隠密策定+公表タイミング〟を設計せよ
可能な限り事前にシミュレーションを行い、労組との対立を過度に煽らないよう極秘体制で準備する。公表時期も綿密に管理し、混乱拡大を防ぐべし。
③協議継続で合法スト要件を潰し〝違法スト〟ラインを死守
議事録に「双方協議中」の文言を組み込むなど、法的正当性を組合に与えない工夫が重要。斡旋プロセスを活用し、正面衝突を回避する。
④弱み(法令・協約違反)は前倒しで是正し交渉カードを奪取
就業規則や残業管理などを一度総点検し、相手に突かれるリスクを封じる。違反が発覚すれば即時改善し、会社としての正統性を高める。
⑤譲歩余地を意図的に残し、三者間協議・裁判での〝落とし所〟を確保
交渉では全方位で防御するだけでなく、最終合意に至る受け皿を用意する。裁判や外部機関の介入を見すえ、双方の軟着陸を図るべし。
※この寄稿は特にインドネシア現地法人経営者やインドネシア進出をご検討の方々に参考としていただくためのものであり、内容の活用の結果について、寄稿者は責任を負いません。(編集部注・この記事に登場する企業や人物は全て架空で実在しません)
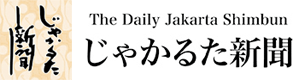




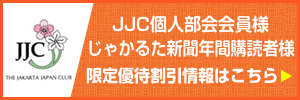


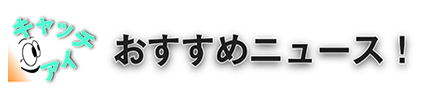












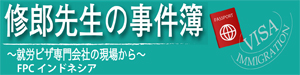





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について