「常に抵抗の意識を」 東京国際映画祭 イの3監督が一堂に
東京・六本木で開かれている第25回東京国際映画祭で24日、インドネシア・エキスプレス部門にそれぞれ2作品を出展しているガリン・ヌグロホ監督(51)、リリ・リザ監督(42)、エドウィン監督(34)の3人が一堂に会した。
エドウィン監督の「動物園からのポストカード」の上映後、作品に関する同監督との質疑応答に続いて、ガリン、リリ両監督が加わり、アジアの風のプログラミング・ディレクターを務める石坂健治さんの司会で、100人超の観客を前に質問に答えた。
50代から30代まで、それぞれの世代を代表する著名監督の3人。ガリン監督は「この映画祭は私にとって家のようなもの。1994年には賞をもらい、3年前には審査員も務めた。東京は友だちのような存在」と説明。さまざまな規制を通じ、表現の自由が阻害されてきたスハルト時代から、体制に抵抗するような形で作品を出し続けてきた経緯を踏まえ、「国民との対話が大切。その必要がなければ映画は作らない。特に創造性を削ぐものに対しては、戦っていく必要がある。かつては軍、今は宗教的なカリスマや消費文化だ」と述べた。素晴らしい作品を輩出する若い世代が出てきているとした上で「これからも、よりわんぱくで抵抗する意識を持った若者が出てくることを望む」とエールを送った。
現実離れしたキャラクターを幻想的な映像で包み込み、性や出自の差別などを鋭くえぐる2作品が上映されたエドウィン監督は、2作とも動物が重要な役割を占めていることについて、「とにかく動物園が好き。今回もまずは上野動物園に行った」という。現在、オランダに留学中で「臭いについて調査している。どうやって映画で臭いという感覚を表現することができるか。しかし、できてない状況。なのでポルノ作品でも作ろうかと思っている」と冗談めかして話し、会場を沸かせた。
2作品のほか、「ティモール島アタンブア39℃」がコンペティション部門に選ばれたリリ監督は、作家性が高い今回のような作品だけでなく、インドネシア最大のヒット作を出し続けてきたことについて、「インドネシアは市場が大きく、たくさんの人が映画館に来るべき。1995年に映画を作り始めたときは、どうやって、映画が大衆のものになるかをミラ(・レスマナ=リリ監督作品のプロデューサー)と考えた。地元の人にどれだけ受け入れられるかが何よりも重要だった」と説明。「映画は芸術の一部でインドネシアは多様な文化を持っている。文化に呼応していく映画人として、予算の大小など、いろいろなやり方があるが、こだわりを持たずにいろいろな作品に挑戦していく」と今後の方針を語った。
世界初公開となった24日夜の「アタンブア」の上映では、400人以上が鑑賞。上映後には、リリ監督とミラ・プロデューサーとの間で質疑応答が行われた。東ティモールが独立を決めてから13年経った現在も、インドネシア側の国境付近にあるアタンブアで家族との離散やさまざまなトラウマを抱えながら前向きに生きる人々の姿を描いた作品は、東ティモールのコエーリョ駐日本大使も鑑賞。「素晴らしい作品」と賛辞を送った。(東京で上野太郎、写真も)
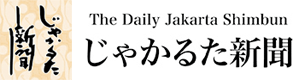









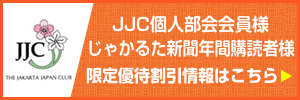


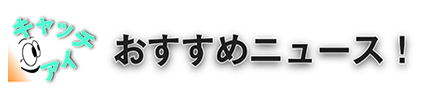












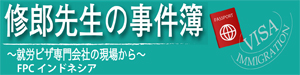





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について