街に再び灯る希望の光 夜のタムリン通りを歩く
11月初旬のある日、深夜におよぶ編集作業を終え、家路を急ごうとバイクにまたがった。だが、そこで思い止まり、夜の首都・ジャカルタを見て歩くことにした。悪夢のような新型コロナウイルスの爆発感染から約4カ月。ワクチン接種の効果なのか、街は平静を取り戻しつつあり、夕涼みをする人々の横顔をこの目で見たくなった。
レバラン(断食月明け大祭)の帰省ラッシュは、インドネシアの風物詩。しかし、コロナ感染で昨年以降、様相は一変した。感染拡大を恐れ、政府は予防策を強化。帰省を禁じた。しかし、私たちインドネシア人にとって家族愛は人生の柱。故郷に向かう人々を止めようもなく、7月に感染爆発を引き起こした。
病院には駐車場にまで感染者があふれ、路上は酸素を求める人の列。コロナは人の命を容赦なく奪った。「ここは戦場か?」。真面目にそう心配した時期もあった。
それだけに9月から始まった感染者の激減は、うれしかった。正直に言えば、保健省発表の数字は水増しではないかと疑うこともあったが、周囲を見渡しても明らかに感染者は減った。西ジャワ州チカランにある居宅周辺も一時、自主的なロックダウンに踏み切ったが、今は平和な日常を取り戻しつつある。
勤務先があるタムリン通り(中央ジャカルタ)の周辺では、あの真っ暗だったアグス・サリム(通称・サバン)通りにも希望の光が灯り始めていた。友だちや家族と食事を楽しむ笑顔がそこにはあった。
「緊急活動制限がレベル1になった11月以降、ジャカルタの空気はがらっと変わった。大声を出さないように。食事は持ち帰りだけ。息苦しさを感じたそれまでの段階的な規制緩和とは違い、ようやく開放された。ようやく街が動き出した。そんな喜びを今、実感している」
サバン通りでマルタバック(ホットケーキ)を売るカキリマ(移動式屋台)の店主、アジさんの笑顔も晴れやかだった。それにつられてか、私自身も気持ちが軽くなり、1日の疲れが癒やされるようだった。
表通りのタムリンに戻り、ホテルインドネシア前にあるロータリーの噴水を目指した。途中、自転車で飲み物を売るウディさんと立ち話をした。
「収入ゼロ。そんな日々が一年以上も続いた。家族が食べる明日の食事もない。そんな不安が続いた。そして今、人が戻り、飲み物が売れる。コロナ禍前には当たり前だった日常が帰ってきた」
もちろん、コロナ禍前とは様相は一変した。保健アプリ「PeduliLindungi(プドゥリリンドゥンギ)」によるワクチンの接種証明はマストで必要。マスク着用も欠かせず、公衆衛生とは遠い世界にいた庶民までも、医学用語を日常生活の中で使うようになった。
そして、国の指導者から道ばたで暮らす人々まで、今の願いはひとつ。もう後戻りをしてほしくない。ようやく取り戻した自由、そして希望を手放したくない。神は人類に厳しい試練を課したが、豊かさにあぐらをかいた甘えを戒め、私たちはきっと乗り越えていく。そう信じている。(センディ・ラマ、写真も)









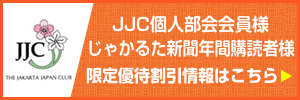





















 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について