再訪 機械油がにおう街 中央ジャカルタ・パサールスネン
古い道具箱をひっくり返したような街、パサールスネン。火災などの災難を乗り越え、今でこそ買い物客らで賑わう交通の要衝となったが、かつては部品屋や雑貨屋などが軒を連ねるジャカルタ最古の伝統市場だった。それでもこの街を歩いてみると、機械油がにおうような街並みに〝再会〟。軍や警察の払い下げ品を扱う店もあり、東京・上野のアメ横に来たようだった。
中央ジャカルタに位置するパサールスネンで、青果店を営むメリタさん(58)は「コロナのおかげで収入が激減した」という。メリタさんは父親が1970年代に立ち上げた青果店を引き継いだが、「がんばっても、がんばっても、暮らしはよくならない。むしろ悪くなった」と嘆く。
「バン(兄貴)・アリ」の愛称で支持を集め、政治史に残ると言われるアリ・サディキン知事。77年までの10年近い長期政権で、「市民目線の行政」を旗印に近代都市、ジャカルタの都市基盤を築いた。
「バン・アリの時代、パサールスネンの歴史が大きく変わった。ゴミ箱のようだったこの街は、市場整備が進んで街が活気を取り戻した」
メリタさんの父親も、その波に乗って野菜売りを始めたが、80年代になると状況が変わった。「街を作り替えると再開発の大号令が鳴り響き、パサールの再建が始まったが、喜んだのは建設に関わる金持ちばかり」。人の流れが変わり、確かに新しい市場は衛生的だったが、賃料や電気代などが発生。「客は減って借金ばかりが増えていった」。
メリタさんは「せめてコロナがなければ…」と力なく言い、今、廃業か存続かという厳しい判断を迫られているという。
メリタさんの店の近くで、テレビの解体作業をしていたブディさん(44)に話しかけてみると、言葉は少なく、表情は険しい。なんでも部品取りも法律で規制が厳しくなり、人目を避けての作業になる。「それでも生活があるからな」。そう吐き捨てるように言ったまま、貝のように口を閉ざした。
一方、中古楽器を売るワヒョさん(30)の表情は明るく、客の呼び込みにも熱が入っていた。新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務の人が増え、商売も順調なようだ。
「この街も時代の流れの中で変化する。止まっていては始まらないよ。楽器だけでなく、いろんな可能性を試したい」
こう言って差し出してくれたのは空気銃。圧縮空気で弾丸を発射させるポンプ式で、金属製の実銃だから所持は許可制のはずだ。ワヒョさんによれば、「沼に撃ち込んで魚を採る。去年から大流行している」という。しかし、角度によっては水面の表面張力で跳弾となりかねず、かなり危険なはずだ。「だから、未経験者には売らないよう警察の指導を受けている」という。
高層ビルが林立し、近代化が進むパサールスネン。街の様相は時代とともに変化していくが、社会の底辺で生きる庶民は今も生き抜くことで精一杯のようだ。「苦しいよ。でもやらなきゃ。生きているのだから」。老婆のように老け込んだメリタさんの言葉が胸に刺さる。(長谷川周人、写真も)









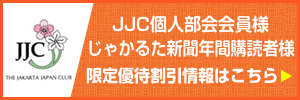





















 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について