インドネシア研究懇話会発足 若手に発表の場 学者・研究者300人登録
日本のインドネシア学者、研究者が一堂に会する「インドネシア研究懇話会」がこのほど発足した。若手研究者に発表の場を設けるのが主な狙い。全国の大学や研究機関から約300人がメーリングリストに登録、会員制はとらず緩やかな相互協力、親睦機関として運営する。語学を除きインドネシア関係の学会が発足するのは今回が初めて。インドネシアが経済的、政治的に台頭するなかで、日本から同国への関心が高まる中、学会への期待も今後強まろう。
研究懇話会の名称はインドネシア語で「Kelompok Pemerhati Peneliti Indoonesia di Jepang」とし、略称は単語の文字から拾ってインドネシア語で船を意味するKAPALとした。代表世話人には加藤剛京大名誉教授、倉沢愛子慶大名誉教授が就任。世話人には太田淳慶大経済学部准教授はじめ5人が就任した。
設立記念の第1回研究大会は昨年12月に京都大学で開かれ、約150人が参加、懇話会への関心と期待の高まりを示した。記念講演では、押川典昭大東文化大学名誉教授、山口裕子北九州市立大学準教授、中村昇平日本学術振興会特別研究員(金沢大学)と3世代の学者が登壇、それぞれの時代を反映した「わたしのインドネシアとインドネシア研究」を論じた。
これまでわが国のインドネシアに関する学界の活動は、東南アジア学会の一部として行われていた。東南アジア諸国の中でこれまで国別学会がなかったのはシンガポール、ブルネイ、東ティモール。インドネシアに関しては1969年に日本インドネシア学会が発足していたものの、同学会の活動対象がインドネシア語教育が中心だったこともあり、インドネシアの社会、文化、政治、経済、歴史をはじめとする学者、研究者たちは研究発表や相互連絡の場を東南アジア学会に求めざるをえない事情になっていた。
しかし、インドネシアへの研究熱が高まる中で、「東南アジア学会では研究成果の発表がまずます限られる情勢になってきたことから、インドネシア専門の学会として独立させることが必要になってきた」(太田准教授)と判断、「インドネシア研究懇話会」として発足した。
当面は事務局も置いていないが、学会としてより形を整える必要もあるとの考えも出ている。(小牧利寿)
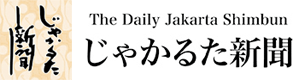




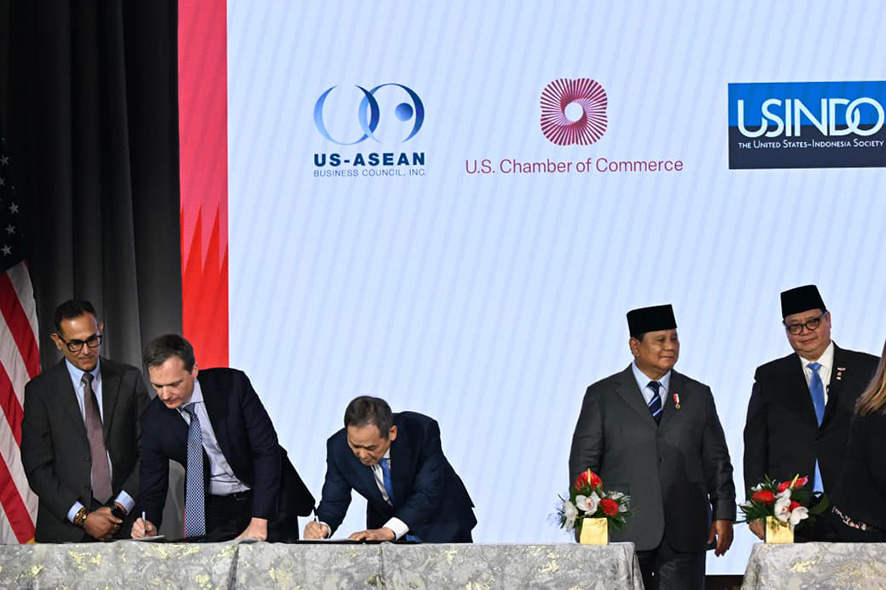


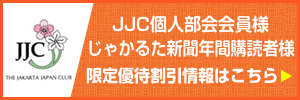







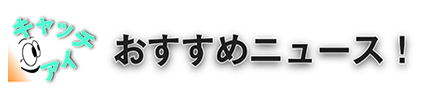







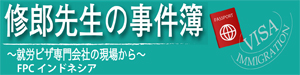





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について