【おすすめ観光情報】命懸けのクジラ漁 フローレス島東方のラマケラ村
東ヌサトゥンガラ州にもりを使った伝統的な方法でクジラ漁を行う村が二つあるといわれている。そのうちの一つ、ソロール島のラマケラ村に足を運び、村の漁師に話を聞いた。
ラマケラ村のある東ヌサトゥンガラ州東フローレス県ソロール島へは同県ララントゥカの港から船が出航している。船に2時間ほど揺られ、港から1時間半バイクタクシーで東に進むと村唯一のモスク「マスジド・アル・ルティハッド」が見えてくる。
村の人口は千人ほど。村人のほとんどは漁師として働き、アジやサバなどの回遊魚を村の市場で売って生活している。3年前にやっと水道と電気が開通した小さな村だ。
村に到着し、港に行ってみると、20年以上漁師として働き、クジラ漁の経験もあるというモハンマド・イドリスさん(43)に出会った。
「僕たちは毎日クジラを捕っているわけじゃなく普段は魚を捕る普通の漁師なんだ。でも、クジラが現れると協力して漁に参加する」とイドリスさん。村に現れるのは体長10〜14メートルのザトウクジラで、捕れるのは多くて年間10頭だという。
「だからクジラが捕れると町中お祭り騒ぎになるんだ」と笑う。クジラが捕れると、頭部から腹部は捕鯨に参加した漁師の分、腹部から尾びれまでは村人の分とするルールがあり、村全体でクジラを分け合っている。
クジラ漁の方法は漁が始まった400年前から変わっていない。イドリスさんの紹介で捕鯨用の道具を先祖代々作ってきたというアルファンさん(51)の家を訪れると、捕鯨に使用するT字状のかぎ、もり、曲線のかぎを見せてくれた。2種類のかぎが全長40センチほど、もりが30センチほどで、竹棒や綱にくくりつけて使われるという。
アルファンさんは「漁で最初に使うのはT字状のかぎ。漁師はクジラに近づくと海に潜り、かぎをクジラの体に食い込ませ逃げないようにする」と説明した。「次にもりを使って心臓の辺りを何度も突き、クジラを弱らせる。最後の曲線のかぎはクジラを船に固定して陸に上げるのに使われるんだ」
相手は巨体。捕鯨には常に危険が伴う。ゾルファンさんによると2年前には陸に上げるため船に固定していたクジラが突然暴れだし、船ごと海底に引きずり込まれる事故もあったという。「クジラも生きようと必死だからね。でも、漁師も回遊魚だけでは稼げないから必死だよ」。捕鯨は漁師にとってもクジラにとっても死ぬか生きるかの命懸けの戦いだ。
しかし、近年この伝統漁が脅かされようとしている。漁の残酷さやクジラの個体数の減少を背景に欧米の環境団体が批判を強めているためだ。村にはことしに入り、国際社会の批判をかわしきれなくなった海洋水産省から漁獲量を減らすよう通達があった。
村の漁師アルワン・カハールさん(57)は「これまで守ってきた村の伝統を壊すわけにはいかない。金を稼げるクジラが捕れなくなれば、われわれの生活が成り立たない」と頭を抱える。他の漁師に声を掛け、政府に対する抗議活動を計画しているという。(泉洸希、写真も)
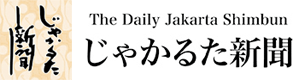




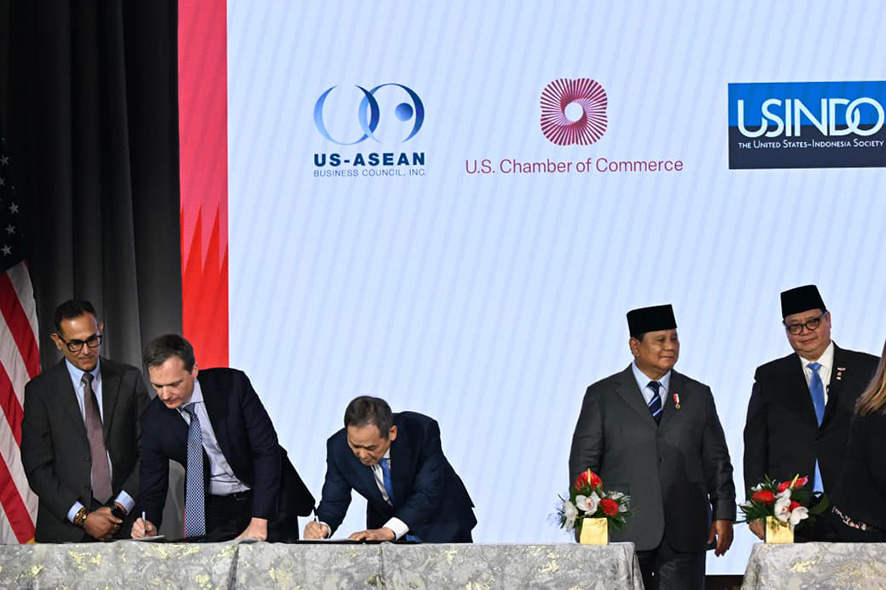


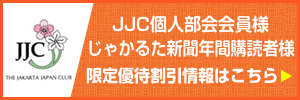







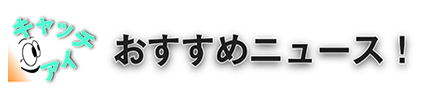







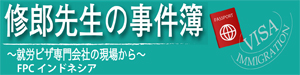





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について