【ガンプラ最前線 in インドネシア(中)】 ゼロから1への技術 「過度期」に指南書出版
プラモデルは、箱の中のパーツを組み上げるもの――という常識が覆された。バンテン州タンゲラン県のガディン・スルポンでガンプラ教室を運営するイファン・クシアントさん(32)は「今は過渡期」と分析するが、インドネシアのガンプラ文化は予想を超えて急速に発展している。
ルコ(住居付き店舗)の一角にある「ブルブレック・スタジオ」。入り口から作品が展示されているガラスケースを横目に抜けると、6畳ほどの作業場がある。数々の工具が並ぶ机の上には、緑色の使い込まれたカッティングマット。接着剤やアクリル塗料の匂いがうっすら漂う。
「普段していることを説明するよ」とイファンさん。おもむろに厚さ1ミリの白いプラスチック板を取り出し、油性の細いマーカーを使ってフリーハンドで侍の前掛けのような形を描いた。アクリルカッターを5度なぞるように引き、入った切れ込みを中心に折ると、ガンダムの腰部分の前掛けのような部品があっという間にできあがった。
ガンプラを作り始めたのは2011年。仲間うちとのサッカー試合で脚に全治5カ月の重傷を負い入院生活が続いた。外出できないストレスを解消してくれたのがガンプラだった」と振り返る。ガンプラを作っていた弟に勧められたことがきっかけだった。
素材から部品を作り、それを組み立てて模型を作る手法は「スクラッチビルド」と言われ、イファンさんは「0(ゼロ)から1を作り出す技術」と話す。これまで日本のプラモデル雑誌や動画をインターネットで見て研究を重ねてきた。14年にかねて交流のあったシンガポールのプラモデル用工具用品店から専門書を書かないか、と打診があり、英語版の指南書「スクラッチビルド・レボリューション」が生まれた。
「専用の道具が数多く販売されている日本でなく、ここはインドネシア。誰でも入手できる道具で代用する方法も紹介している」。指南書は、昨年4月の発売から計20カ国で約2千冊を売り上げた。昨年7月からはスタジオの2人とともに、MG(マスターグレード、1/100スケール)では未発売のガンダム大型支援機の自作ガンプラ制作にあたっている。
インドネシアのガンプラ文化は、13年のアニメ「ガンダムビルドファイターズ」放送から拡大した。イファンさんが「過渡期」と分析したのは「興味を持つのは裕福な人が多く、他の層に広まるかが鍵」という理由だ。
スタジオでは、指南書の内容をインドネシア語で解説しながら計12項目の技術を教える。「教室と言うより、話し合って質を高め合う。みんなで作り上げることが大切」と強調する。「(生計を立てられる)プロを目指しながら、文化を広めていきたい。ストレス発散になり、ゲームより集中力がつく。本当に素晴らしい」と白い歯を見せた。(中島昭浩、写真も、つづく)
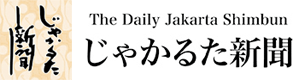






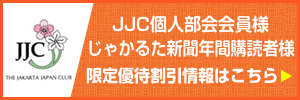







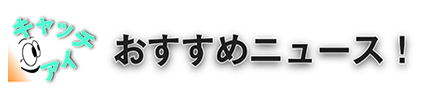







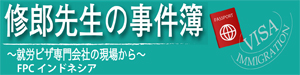





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について