【100年目の挑戦 スラバヤ動物園(上)】「死の動物園」再起へ 動物のデータがない 管理体制改善
動物の死が相次ぎ、飼育環境や管理体制が問題視されてきた東ジャワ州スラバヤ動物園。「死の動物園」のレッテルを貼られて以来、再起に奮闘する職員がいる。来年開園100周年を迎える国内最大級の動物園の今を追った。
オランダ植民地時代の1916年に設立されたスラバヤ動物園(東ジャワ州)は国内で2番目に古く、15ヘクタールの広大な敷地を持つ国内最大級の動物園。インドネシア固有のコモドドラゴンやバビルサなど希少動物を含む約210種類2300頭を飼育している。学校の遠足の定番として市民は子どものころから親しみ、年末年始やレバラン(断食月明け大祭)には各地から1日2万人が訪れる。
しかし近年問題が続出した。2010年、日光があたらない過密状態のおりで飼育されていたコモドドラゴンの赤ちゃん13匹が死んだ。昨年1月には、生後18カ月の雄のアフリカライオンがロープで首をつった不自然な状態で死んでいるのが見つかった。
「死の動物園」。国内外のメディアが大々的に報道し、いったん否定的なレッテルが貼られると客足は遠のいた。劣悪な飼育環境や経営陣の汚職などが次々と発覚。2013年まで園長を務めたトニー・スマンパウは、動物を車と交換するなどの不正取引が疑われ、スラバヤ市のトリ・リスマハリニ市長が汚職撲滅委員会(KPK)に告発した。動物園を管轄する林業相の意向で、管理運営はスラバヤ市公社へ移管された。
■動物保護の専門家
運営体制の改善を目指す中、ことし4月、アセタ・ブスタニ・タジュディン(45)が臨時園長に就任した。14年9月に外部から運営部長として迎えられたばかり。同園で唯一、動物・環境保護活動の経験を持つ専門家だ。
アセタは91年に東カリマンタンで友人3人とともにボルネオ・オランウータン・サバイバル・ファウンデーション(BOSF)を立ち上げた。夫の転勤でスラバヤに移住するまでの20年以上、住民に捕獲されるなどしたオランウータンを保護し、リハビリして森に返す活動を行ってきた。
14年7月、インターネット上にたまたま現れた求人広告がスラバヤ動物園の運営部長職だった。「私は人と働くよりも動物と働く方が好き。やってみよう」と即決した。9月に赴任した当初、設備はおりの内部など部分的な改修は必要だが、報道で聞いていたほど悪くないように見えた。一方で園の管理体制など体質的な問題が気になった。
当時の動物の死亡率は25〜30%。動物の状態を確認しようとしたがデータベースの管理が不十分で分からなかった。ワシントン条約で保護対象とされているバタグールガメ688匹、マレーハコガメ570匹との記録は2004年から10年間更新されていなかった。「園を立て直すには、まずは動物を知ることから」。動物園の再生に向けた挑戦が始まった。(木村綾、写真も)(敬称略、つづく)
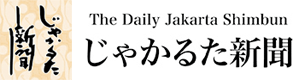






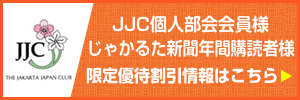







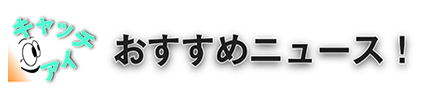







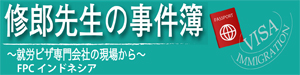





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について