米軍機と一触即発も チャッピー元空軍参謀長 03年に異例の公表
2014年に空軍が強制着陸させた外国機はいずれも民間機だったが、東ジャワ州上空では03年、米空母艦載機5機を迎撃した空軍機が攻撃用のレーダー照射を受ける事件も起きている。軍は当時、それまで公にされることのなかった領空侵犯の事実を記者会見で発表した。「国際的関心を集めようと公表に踏み切った」と振り返るのは、当時空軍参謀長だったチャッピー・ハキム氏だ。
事件は03年7月3日夕方、同州バウェアン島上空に進入した外国機をレーダー探知したのが発端。同州マディウン基地からF―16戦闘機2機が緊急発進し、米海軍のF―18戦闘機を確認した。米軍機はF―16のうち一機にレーダー照射。このF―16は回避行動を取るとともに、もう一機が支援に回るなど、双方の通信が成立するまでの数分間、一触即発の事態に陥った。
このほど取材に応じたチャッピー氏は、以前から米軍機による領空侵犯は頻発していたと明らかにした。背景にはインドネシアが設定した「群島水域」をめぐる両国の主張の違いが背景にあるとみられるという。
群島水域は島と島を結ぶ線の内側全体をその国の水域とするもの。イ政府はジャワ海を南北に貫くマカッサル海峡とスンダ海峡を航路に設定し、外国の船や航空機の通航に充てていた。軍艦の航行を制限される米国は東西の航路設置を要求していたが、受け入れなかった。これに反発した米軍は航路外の航行を繰り返していたとみられる。実際、この日緊急発進した空軍機も東に向かって進む米海軍の艦隊を確認している。
チャッピー氏が「以前は外国機の侵入を公表することはなかった。例外的にあったとしても、相手国との話し合いが妥結した後、内容もすり合わせてからだった」と振り返る当時、一方的な会見は異例の出来事だった。それでも同氏は「米国寄りの世論が多い中での発表だったが、以後、米国による無許可飛行はなくなった」と話し、公表による成果だったと強調した。(道下健弘、写真も)
■伸び続ける国防費 日本や近隣国も注視
強制着陸の件数増加の背景にある国軍の装備増強。ジョコウィ政権は国防予算を国内総生産(GDP)の1.5%に高める目標を掲げており、この流れは今後も続きそうだ。
国防費は過去10年、伸び続けている。ユドヨノ政権が組んだ15年予算は96兆8千億ルピア(約9千億円)、GDP比は0.9%だった。新政権はこれをさらに高めることを目指す。
前政権下の13年、シンガポールであったアジア安全保障会議(シャングリラ会合)で講演したプルモノ国防相(当時)は、国防費の伸びを「『失われた10年』で生じたギャップを埋める」ものと説明。アジア通貨危機以降、経済政策に重点を置く一方で後回しになった軍の近代化を進めているとして、正当性を主張した。ジョコウィ氏も大統領就任後、「国防支出の増加は国内産業の成長に寄与する」などと述べ、積極的に予算増を進める方針を取っている。
装備の調達を加速するインドネシアに対しては、外国の関心も高い。先月末にジャワ海に墜落したエアアジア機の捜索では、ロシアがジェット飛行艇を派遣。海洋監視能力の向上を目指すインドネシアは同機種の購入に前向きな姿勢を見せており、露骨な売り込みとして注目を集めた。防衛装備移転三原則を閣議決定し、実質的な禁輸方針を緩和した日本も昨年11月、防衛省が装備輸出に向けた協議を進めることでイ国防省と合意した。
国軍に対する近隣国の見方も変わってきているようだ。豪州は12年7月、同国主催の共同演習にインドネシア空軍のスホイ戦闘機を招き、空軍の能力向上を評価した。豪州はインドネシアを13年の国防白書で「地域で最も重要な関係」と表現し、信頼構築を進める姿勢を示している。
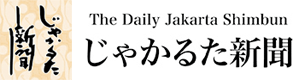








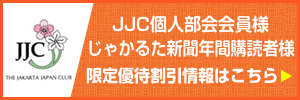


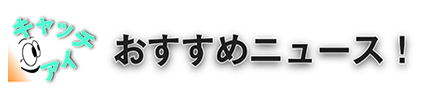












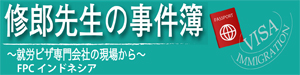





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について